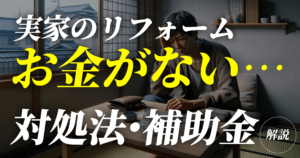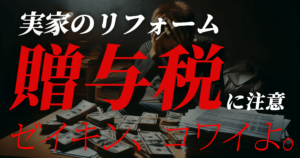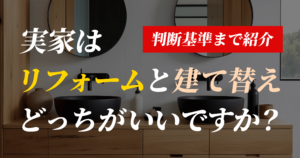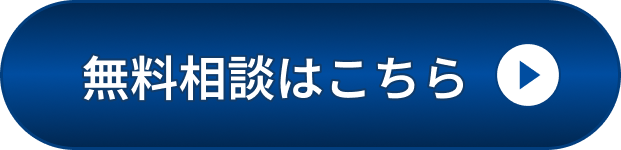実家を二世帯住宅へリフォームする際、間取りや費用、注意点などに関して疑問や不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。
二世帯住宅で仲良く暮らしていくためには、間取りが大切です。二世帯住宅の間取りには、完全分離型や部分共有型、完全共有型、平屋などさまざまな方法があります。
二世帯住宅のリフォームでは、各世帯が仲良く、快適に過ごせる間取りを考えることが大切です。間取りを考える際に気を付けた方が良いポイントや注意点を知っておかないと、後悔してしまう恐れがあります。
そこで、本記事では二世帯住宅のリフォームの間取りを考える際の気を付けた方が良いポイントや注意点について詳しく解説していきます。他にも費用や参考例も紹介します。実家をリフォームし、二世帯住宅へしようと検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

リノベーションハイムでは、リフォームの無料相談を受け付けています。
50年以上の歴史と豊富なリフォーム実績からお客様のご要望に応じたリフォームを実現します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
実家を二世帯住宅にする3つのリフォーム方法
実家を二世帯住宅にするリフォーム方法には種類があります。お風呂や玄関など一部を共有するのか、寝室以外すべて共有にするのか、1階と2階で完全に分けてリフォームするのかなど、各家庭によって最適なものは異なります。
大きく分けると以下3種類あり、その内容を下記表にまとめました。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 完全分離型 | 生活空間を完全に分離。 各世帯専用の生活空間・住宅設備がある。 |
| 完全共有型 | 生活空間・住宅設備を完全に共有。 各世帯専用の空間は個室のみ。 |
| 部分共有型 | LDKなどの生活空間、お風呂、キッチンなどの住宅設備の一部を共有。 |
二世帯住宅へのリフォームを考える際は、食事を一緒にするのか、キッチンや浴室、トイレ、玄関、廊下は共用でも問題ないか日常生活を想像しながら考えてみてください。
①完全分離型
完全分離型は、玄関やキッチン、お風呂などすべての生活空間を世帯ごとに分離するスタイルです。世帯ごとの居住スペースを左右や上下に分ける間取りパターンがあります。
親世帯と子世帯でライフスタイルが大きく違う場合や、価値観が異なり、プライバシーを重視したい場合におすすめです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・費用を分けやすい ・両世帯のプライバシーを確保しやすい ・上下分離型の場合、土地を有効活用できる | ・二世帯合計で高額になる ・広さが必要 ・他の方法と比べて、設備費がかかる |
完全分離型の住まいで暮らしやすくするポイントは、生活音です。生活空間を上下に分ける場合はより生活音に配慮が必要になります。子世帯の空間を2階に設ける場合には、寝室の上の部屋は注意すると良いでしょう。
②完全共有型
完全共有型は、玄関やリビング、キッチンなど基本的な生活空間をすべて共有し、一緒に暮らすスタイルです。家族団らんで楽しく生活を送れたり、建築費用やランニングコストが削減できます。
しかし、生活スタイルや価値観が違う場合は、お互いストレスになってしまうので、プライバシーをある程度確保しておきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・費用を抑えやすい ・リフォームしやすい ・プライバシーが守られる ・お互いを手助けしやすい | ・費用分担の話し合いが必要 ・お互いの生活習慣が守りにくい |
完全共有型で暮らしやすくするためには、居場所の確保がポイントです。どちらの親と一緒に住むのかもポイントですが、それぞれのプライバシーを考慮して居場所を作りましょう。
③部分共有型
部分共有型は、キッチンや浴室・トイレなど一部の設備を別に設置し、玄関は一緒に使用するなど、住宅設備を共有するスタイルです。住宅のどの部分を共有するかは、各家族の生活様式に合わせて考えてみてください。
光熱費を節約したい方は、浴室を一緒にすると効果的です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・予算に合わせて費用を調整しやすい ・両世帯の独立性を考慮した間取りにできる ・プライバシーと便利さが備わっている ・生活リズムの違いを気にしなくて良い ・家事を上手く分担しやすい | ・共有部分の選択によって高額になる場合がある ・共用部分が狭くなる ・プライバシーを完全に確保できない ・将来的に一世帯で住むとなった時に、使わないスペースができる |
部分共有型で暮らしやすくするためには、洗面所や玄関収納がポイントです。忙しい時間帯に混雑しないような間取りや、収納問題でストレスが溜まらないよう工夫しておきましょう。
実家を二世帯住宅にリフォームする際の費用相場
上記では二世帯住宅のリフォーム方法について紹介しましたが、それぞれの費用相場について解説していきます。
二世帯住宅をリフォームする際の費用相場は1,000万円以上が一般的です。工事期間としては1〜3か月程度が目安になります。
| 項目 | 費用相場 | 工期 |
|---|---|---|
| 完全分離型 | 2,000万円~3,000万円 | 5カ月 |
| 完全共有型 | 1,000万円 | 3カ月 |
| 部分共有型 | 1,500万円~3,000万円 | 3カ月 |
これはあくまで目安です。各家庭には予算があるはずなので、予算と要望に合ったベストな選択肢を選ぶことが大切です。
実家を二世帯住宅にリフォームした間取り事例3選
実家を二世帯住宅へリフォームした事例を3つピックアップしました。
二世帯住宅へのリフォームを検討している方は参考にしてみてください。
①『うち』と『そと』 ワンストップデザイン
こちらは、大田区に建つRC造2階建ての2世帯住宅です。それぞれの世帯毎にデザイン性、住宅性能を向上させ、大規模リフォームしました。
1階のご主人世帯は殆どプライバシーがなかったため、寝室の先に小上がり和室を設けています。また、ご主人の書斎を作ったり、夫婦が1人の時間を過ごせる工夫がされています。
1階は親世帯向けに、2階は子世帯向けに間取りやデザインが考えられています。共働きの夫婦のために、家事導線を工夫しているのもポイントです。
②ゆとりを持って健康で快適に、楽しく暮らせるモダンな住まい
こちらは、横浜市にある、築30年の住宅のリフォーム事例です。3世代がゆとりを持ち、健康で快適に、楽しく暮らせるモダンな住まいへ一新しました。
LDKの分離型から約22畳の一体型LDKに変更し、住まいの中心となっています。木の素材感を生かした空間にアクセントウォールをプラスして、3世代が心地良く暮らせる空間に。
家族みんながリビングに持ち込むもので溢れるのを防ぐため、リビングにクローゼットが配置され、空間が美しく保たれています。
③高齢の両親が暮らしやすい、バリアフリーの二世帯住宅
こちらは、高齢の両親が暮らしやすいバリアフリーの二世帯住宅へリフォームされました。家全体の間取りを一から見直し、頑丈なつくりの重量鉄骨造を活かしたスケルトンリフォームが行われています。
廊下や開口部を広く取り、開閉しやすい引戸を採用するなど、これからの生活へ配慮しつつ、モダンな美しさと機能性が備えられているのもポイントです。随所にご夫婦の好きなアジアンテイストを取り入れ、暮らしの豊かさも追求しています。
実家を二世帯住宅にする際の間取りの考え方・ポイント5選
二世帯住宅の間取りの考え方や、考えるポイントを以下5つ紹介します。
このようなことを考えながら、二世帯間で話し合いをして決めていきましょう。
①プライバシーの確保
完全分離型ではなく、共有部分がある場合に起こりやすいのが、プライバシーを確保するのが難しいことです。同じ家の中に2世帯住んでいるため、世帯間の目や生活音などを気にして過ごしたり、顔を合わせる時や帰宅時間など行動にも気を遣うこともあります。
共有部分が多いと、家事の方法や子育ての方針など常に見られているストレスを感じる場合も多いです。
予算などの関係で、完全分離型にできない場合は、同居前に価値観をすり合わせたり、ライフスタイルを伝え合っておきましょう。
②光熱費の折半
完全共有型の場合、光熱費は節約できます。なぜなら、二世帯住宅は必要な設備が1つで済んだり、水道や電気、ガスなどのメーターもまとめられ、基本料金が一棟分に抑えられるからです。
工事費用に関しても、一世帯分でまとめられると、引き込みの工事費用やメーター費用などの初期費用が節約できます。
しかし、水道や電気、ガス以外にも電話代や住宅ローンなど発生する経費は多いです。お金に関する内容はシビアなので、同居前に負担の割合を相談しておきましょう。光熱費を半分にする家庭が多いです。
③テレビなどの占有
リビングを共用にする場合、テレビで問題になることも多いです。好きな番組が同じであれば問題ありませんが、誰かが1人で占有してしまうと不満が出てきます。
部屋やキッチンなどの設備は共用でも、テレビや冷蔵庫などの家電は2つ用意しておくなど工夫を加えて、事前に対処しておきましょう。
④収納部分の使い分け
収納スペースの利用方法は盲点になりがちですが、大切です。収納はどれだけあっても足りないと思うことが多いため、一世帯だけで使うのも工夫が必要です。
二世帯で使うとなると、どんどん収納場所がなくなってしまいます。特に、玄関や洗面所の収納は問題になりやすいので要注意です。ここは誰のスペースなのかなど事前に意見を合わせておきましょう。
⑤生活時間の違い
二世帯住宅では、親世帯と子世帯で生活時間が違うことが多いです。共有の玄関など、生活動線に共有部分があると、生活音がストレスになることもあります。
もしくは、生活音に気を遣いながら生活しないといけません。そうなると、お互いストレスが溜まってしまいます。
音だけでなく、臭いが気になることもあるので、気になる場合は間取りを工夫したり、換気扇や吸気口の数を増やしたり、位置を変更したりして事前に防ぎましょう。
実家を二世帯住宅にリフォームする費用を抑える方法
費用相場をみると、費用負担の大きさに不安を覚えた方もいるでしょう。
現在、国は良質な住宅を増やすことを目的とし、リフォームや新築に関する補助金や減税制度を実施しています。二世帯住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度を活用して、費用負担を抑えましょう。
補助金を利用する
二世帯住宅のリフォームを対象とした主な補助金制度は以下5つです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 主に子育て世帯のリフォーム |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 耐震性能や省エネ性能の向上など |
| 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 住宅を高断熱化 |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ性能を高める断熱材、窓、ガラスに交換 |
| 各地方自治体が実施している制度 | 自治体によって内容が異なる |
※参考:国土交通省「住宅リフォームの支援制度」
補助金を上手く活用することで、工事の質を高め、少しでも費用を抑えてリフォームできます。補助金の実施状況は、受付終了や再受付、新設など変動するため、申請をする前に最新情報をチェックしておきましょう。
調べてもよく分からない場合は、リフォーム会社に聞いてみてください。
減税制度を利用する
二世帯住宅のリフォームを対象とした主な減税制度には以下のようなものがあります。
- 住宅ローン減税
- 固定資産税の優遇措置
- 登録免許税の優遇措置
- 登録免許税の優遇措置
- 不動産取得税の優遇措置
- 贈与税非課税措置
減税制度は、対象となるリフォーム工事を実施することで、その年の所得税から直接控除される仕組みです。毎年の固定費を抑えられます。
国や地方自治体の助成金と上手く併用することで、さらにお得にリフォームが可能です。減税制度の実施状況は国の政策によって変動するため、申請する前にチェックしておきましょう。
相続税の控除
土地の価値を下げる「小規模宅地の特例」というものに基づき、親と一緒に住んでいる二世帯住宅には、土地の評価額が80%も減額されます。
2015年1月から相続税の基礎控除額が縮小され、対象となる土地面積が240㎡から330㎡に広がりました。二世帯住宅の土地は100坪まで相続税が削減できます。
つまり、二世帯住宅にして、子どもが親と同居し、親名義の自宅土地を相続すると税金が80%も減額されます。
不動産取得税の軽減
実家をリフォームする際、不動産取得税が発生します。通常であれば、50㎡以上240㎡以下の床面積で要件を満たす場合、一世帯あたりの不動産価格から1,200万円が控除されます。
それぞれ独立した二世帯住宅と認められると、控除を2戸分、2倍の額で受けられます。二世帯住宅の条件は、各自治体によって異なりますが、以下のようなものが挙げられます。
- 世帯ごとに専用の玄関がある
- トイレが別々
- 世帯間の通路が扉などで仕切られている
上記のような内容に加えて、構造上の独立性があるかどうかが確認されます。
固定資産税の軽減
1世帯当たりの土地の固定資産税は、200㎡までの場合、土地の評価額の6分の1まで軽減されます。しかし、200㎡を超える場合は評価額の3分の1までしか軽減されません。
固定資産税もそれぞれ独立している二世帯住宅と認められると、2戸分で計算されるため、税制の対策ができます。
実家を二世帯住宅にリフォームするならリノベーションハイムにおまかせください
実家を二世帯住宅にリフォームする際は、リノベーションハイムにおまかせください。
リノベーションハイムは過去にたくさんの二世帯住宅リフォームへ携わっています。また、アフターサービスも充実しているため、リフォーム後も安心して暮らしていただけます。
豊富な実績と丁寧なカウンセリングで、トラブルのないリフォームを目指します。無料の相談も実施しているので、興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。
まとめ
本記事では、二世帯住宅のリフォームについて間取りや費用相場、考え方などについて解説しました。二世帯住宅へのリフォームは仲良く快適に暮らしていくために、各世帯のライフスタイルを考慮し、間取りやデザインを考えることが必要です。
二世帯住宅へのリフォーム後、仲良く快適に暮らしていくために、本記事の内容を参考にリフォームプランを立ててみてください。二世帯住宅のリフォームについては、リノベーションハイムにお気軽にご相談ください。
本記事があなたのお役に立てることを願っております。