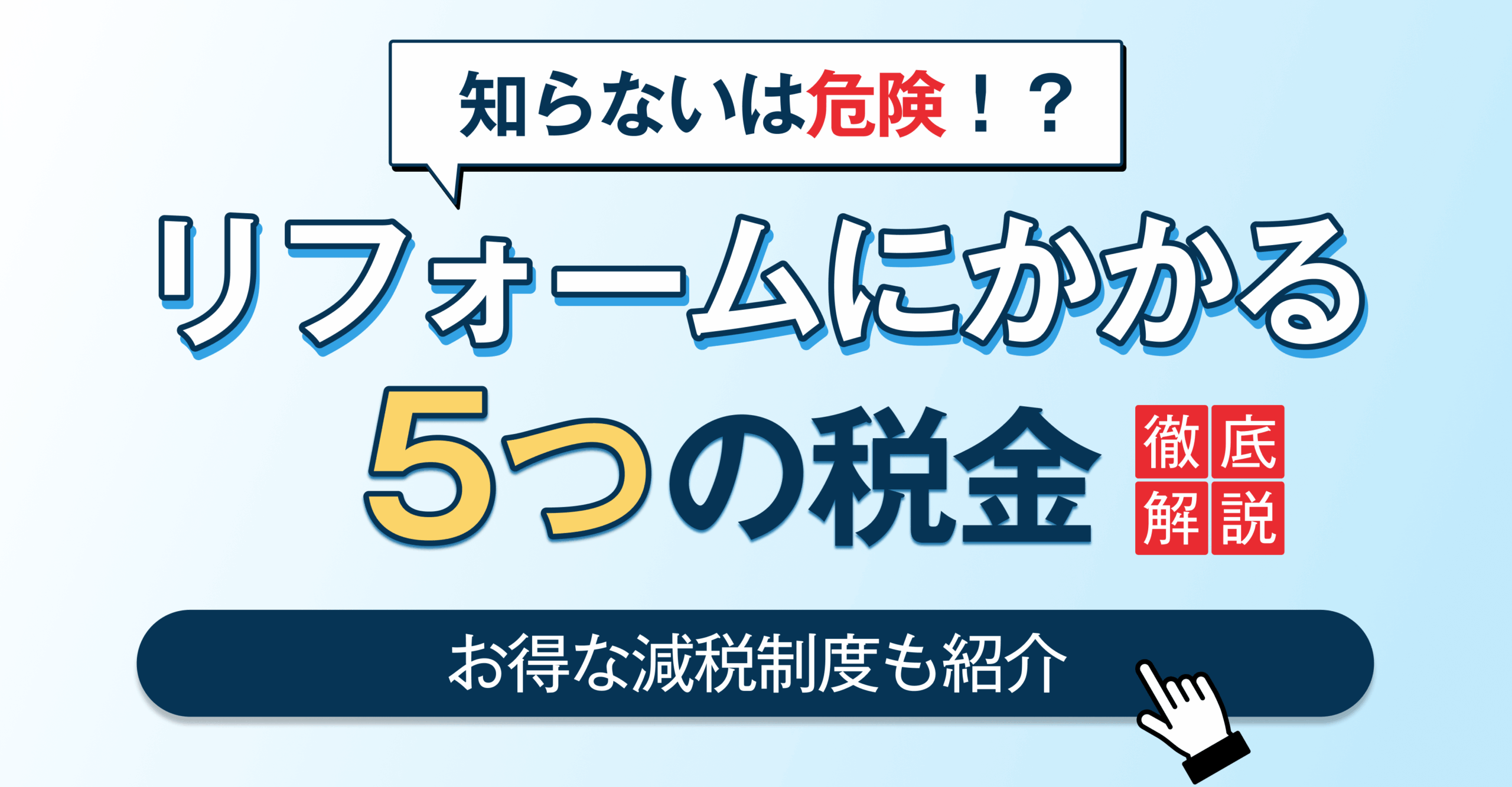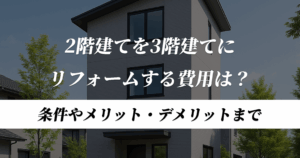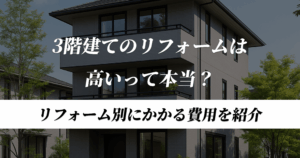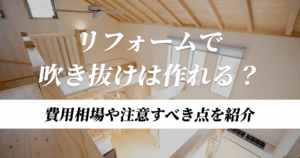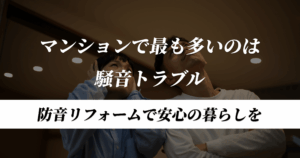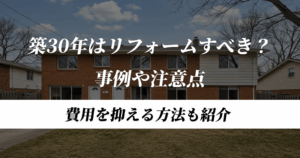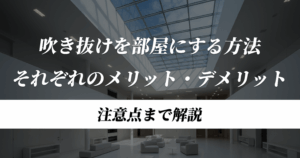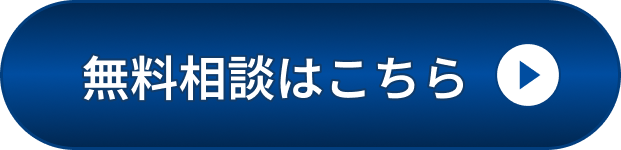主婦Aさん
主婦Aさんリフォームするとかかる税金ってなに?
リフォームの税金を抑える方法ってあるの?
リフォームを実施する際に、かかる費用を気にかける方は多いでしょう。予算内に抑えるために、リフォーム内容や実施場所を検討する方も多いはずです。
ただし、リフォーム費用以外に把握しておくべきなのが、税金です。なかには、リフォームによって税金が上がる場合もあり、想定外の支払いに困惑しかねません。
そこで、本記事ではリフォームの実施でかかる可能性のある税金を、納税額を抑える方法や減税制度を交えて紹介します。あわせて、リフォームの税金における注意点やよくある質問にも答えるので、ぜひ参考にしてください。
リフォームすると税金ってかかるの?


結論、リフォームの実施により税金がかかる場合があります。なぜなら、リフォームを行うことで、贈与になることや手続きが必要なこともあるからです。
たとえば、親所有の実家を子が負担してリフォームする場合、贈与とみなされると贈与税がかかることがあります。また、自己所有の家でも住宅ローンを組んでリフォームを行えば、登録免許税がかかる可能性があるのです。
そのため、リフォーム費用のみに気をとられると想定外の税金が発生し、困惑することがあります。そこで、次の見出しではリフォームでかかる可能性のある税金やおおよその金額を紹介します。
リフォームの実施でかかる可能性のある5つの税金
想定外の出費にならないよう、リフォーム前にかかる税金について確認しておくのが賢明です。そこで、ここからはリフォームの実施でかかる可能性のある税金を、5つ紹介します。
不動産取得税
不動産取得税は、リフォームの実施でかかる可能性のある税金の1つです。不動産取得税とは、土地や家の購入または贈与などにより不動産を取得した際にかかる税金を指します。
リフォームの例では、家の増改築を実施した際に家の価値が上昇すれば不動産取得税がかかります。不動産取得税は都道府県税であり、東京都の場合にかかる金額は次のとおりです。
不動産取得税=固定資産税の評価額×3%
リフォームによる不動産取得税の有無は、家の評価額が上昇するとかかることを覚えておきましょう。
登録免許税
リフォームにより、登録免許税がかかることもあります。登録免許税とは、登記にかかる税金です。登記は、不動産に関する情報を法務局の帳簿に記録し公開する制度を指します。
住宅ローンを利用してリフォームを行う場合には、土地や家を担保にする抵当権を登録します。抵当権の登録にかかるのが、登録免許税です。登録免許税は国税であり、次のような金額を納税します。
登録免許税=借入金額×0.4%
住宅ローンを組みリフォームを実施する場合には、登録免許税が欠かせません。
贈与税
贈与税も、リフォームの実施でかかる可能性があります。贈与税とは、贈与により財産を取得した際にかかる税金のことです。
たとえば、親所有の実家のリフォーム費用を子どもが負担する場合には金額次第で贈与税がかかります。贈与税の基礎控除額は年間110万円であり、もし110万円を超えるリフォーム費用がかかる場合には、贈与税が避けられません。
贈与税は、金額に応じて次のように税率が変わります。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
具体的には、基礎控除後の課税価格が400万円の場合、次のような計算です。
400 × 15% – 10万円 = 50万円
他の所有者の家をリフォームして費用が110万円を超える場合には、贈与税がかかることを念頭におきましょう。
印紙税
印紙税も、リフォームの実施でかかる可能性のある税金の1つです。印紙税とは、契約書や受領書に課税される税金を指します。
リフォームの場合には、契約を行う際に作成される契約書に印紙税がかかるのです。記載された契約金額により、次のように印紙税が異なります。
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円以上50万円以下 | 400円 |
| 50万円以上100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円以上500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円以上1000万円以下 | 10,000万円 |
契約金額次第では、印紙税がかかることも覚えておきましょう。
固定資産税
固定資産税も、リフォームを行うとかかる可能性があります。固定資産税とは、土地や家の所有者にかかる税金です。
家や土地を所有すれば、固定資産税は必ずかかります。加えて、増築リフォームにより床面積が増加すれば、評価額も上がり固定資産税は増額されます。固定資産税は、次のような計算方法で算出します。
固定資産税=評価額×1.4%
固定資産税は家を所有すれば必ずかかるものの、増額になるかはリフォーム内容次第です。
リフォームにかかる税金を抑える方法
リフォームにより納税額が増えるなら、可能な限り増額を抑えたいと感じる方もいるでしょう。そこで、ここからはリフォームにかかる税金を抑える方法を、3つ紹介します。
住宅ローン減税を利用する
住宅ローン減税は、リフォームにかかる税金を抑える方法のひとつです。住宅ローン減税を利用することで、所得税を低く抑えられるのです。
リフォームの場合、ローンを組むと年末のローン残高の0.7%を所得税から10年間控除できます。借入限度額は2,000万円です。
もし、所得税で控除しきれない場合には、住民税からの控除もできます。10年間控除され続けるため、リフォーム費用でローンを組む場合には住宅ローン減税を利用するのが賢明です。
投資型減税を利用する
リフォームにかかる税金を抑えるには、投資型減税を利用する方法もあります。投資型減税を利用すると、所得税が減税されます。
投資型減税とは、自己投資で住宅を改修する場合に所得税が減税される制度です。投資型減税を利用するには、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化のいずれかのリフォームを実施する必要があります。
投資型減税を利用できれば、リフォーム翌年に最大で50万円を所得税から減税されるのです。住宅ローンを組まないでリフォームをするなら、投資型減税を利用することをおすすめします。
贈与税の非課税枠を活用する
リフォームにかかる税金を抑えるには、贈与税の非課税枠を活用するのが重要です。贈与税の非課税枠を活用すれば、贈与税を低く抑えられます。
国税庁によると省エネ住宅で1,000万円まで、省エネ住宅以外は500万円までなら贈与を受けても非課税にできます。利用条件はリフォーム費用が100万円以上であり、増改築リフォーム後の床面積が40〜240㎡以下であることです。
贈与税の非課税枠を活用するには、確定申告が必要になります。リフォームの翌年に、確定申告を行い贈与税の非課税特例の適応を受けるのが賢明です。
リフォームにかかる税金は減税できる


先述したように、リフォームには減税措置があり、税金を低く抑えられます。減税制度の利用には申告が必要であり、適切な期間の申告が欠かせません。
国土交通省によると、所得税は確定申告、固定資産税は工事完了3ヶ月以内に自治体に申告する必要があります。とはいえ、減税額はリフォームの種類により異なるため、次の見出しで詳しく紹介します。
減税が利用できるリフォームの種類
ここからは、リフォームの種類別に減税制度と最大控除額を紹介します。
耐震リフォーム(所得税・固定資産税)
耐震リフォームを実施すると、所得税と固定資産税が減税になります。耐震リフォームとは建物の倒壊や損傷を防ぐために、強度を高めるリフォームです。
具体的には、柱や梁といった構造部の補強や屋根の軽量化、接合部の補強などを行います。耐震リフォーム実施の控除額と申請方法は、次のとおりです。
| 控除額 | 申請先 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 最大62.5万円 | 税務署 |
| 固定資産税 | リフォーム翌年のみ前年度の2分の1に減額 | 市町村役場 |
耐震リフォームでは所得税と固定資産税の減税措置があるため、有効活用しましょう。
バリアフリーリフォーム(所得税・固定資産税)
バリアフリーリフォームも、減税が可能なリフォームの種類です。バリアフリーリフォームとは、高齢者や身体が不自由な方が安全に暮らせるように住宅を改修するリフォームのことを指します。
具体的には、手すりの設置や段差の解消、浴室の交換などが該当します。バリアフリーリフォームでの税金控除額と申請方法は、次のとおりです。
| 控除額 | 申請先 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 最大60万円 | 税務署 |
| 固定資産税 | リフォーム翌年のみ前年度の3分の1に減額 | 市町村役場 |
バリアフリーリフォームを実施したら、忘れずに所得税と固定資産税の減税制度を利用するのが賢明です。
省エネリフォーム(所得税・固定資産税)
減税が利用できるリフォームに、省エネリフォームもあります。省エネリフォームとは、断熱性向上や省エネ設備の導入により、エネルギー消費を少なくするリフォームのことです。
省エネリフォームには、高効率給湯器の導入や太陽光発電システムの設置などがあり、CO2排出量の削減ができます。省エネリフォームを実施した際の控除額と申請方法は、次のとおりです。
| 控除額 | 申請先 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 最大67.5万円 | 税務署 |
| 固定資産税 | リフォーム翌年のみ前年度の3分の1に減額 | 市町村役場 |
省エネリフォーム実施で所得税の最大控除額67.5万円を受けるには、太陽光発電システムの設置が欠かせません。太陽光発電システムの設置をしない場合には、最大62.5万円の控除になります。
長期優良住宅化リフォーム(所得税・固定資産税)
長期優良住宅化リフォームの実施でも、減税制度を受けられます。長期優良住宅化リフォームとは、長期優良住宅化リフォームの補助金を活用した断熱性や耐久性などを向上させるリフォームです。
耐震性や省エネ性などが定められた性能基準を満たした場合に、長期優良住宅化リフォームの適応になります。長期優良住宅化リフォームでは、次のような控除を受けられます。
| 控除額 | 申請先 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 最大80万円 | 税務署 |
| 固定資産税 | リフォーム翌年のみ前年度の3分の2に減額 | 市町村役場 |
長期優良住宅化リフォームの控除額が最も大きく、性能基準を満たせば有効なリフォーム方法であるためおすすめです。
子育て対応リフォーム(所得税)
子育て対応リフォームも、減税が利用できます。子育て対応リフォームとは、子どもの安全や安心を確保するためのリフォームです。
具体的には、対面キッチンへの交換や床の防音工事などの実施が子育て対応リフォームに該当します。子育て対応リフォームでは所得税のみ減税が受けられ、最大控除額は62.5万円です。
リフォーム翌年の確定申告期間に税務署で申請を行えば、減税を受けられます。所得税の納税額を抑えられるため、活用するのが賢明です。
三世代同居対応リフォーム(所得税)
三世代同居対応リフォームも、減税が利用できるリフォームの種類の1つです。三世代同居対応リフォームとは、親・子・孫の三世帯が住みやすい住環境を実現するためのリフォームを指します。
具体的には、キッチンや浴室といった水回りの増設や玄関などが複数個所になるよう改修すると三世代同居対応リフォームになります。三世代同居対応リフォームでは、所得税のみ減税を受けることが可能であり、最大控除額は62.5万円です。
親世帯との同居を検討するなら、三世代同居対応リフォームの条件を満たすリフォームを実施することをおすすめします。
リフォームの税金における注意点
ここからは、リフォームの税金における注意点を、2つにまとめて紹介します。
建築確認が必要なリフォームは固定資産税が増額になることもある
建築確認が必要なリフォームでは、固定資産税の増額に注意しなければなりません。建築確認とは、工事着工前に建築基準法へ適合するかを専門機関が審査することです。
スケルトンリフォームや増築リフォームなどでは、建築確認が必要です。建築確認が必要なリフォームを行う場合、評価額が上がれば固定資産税も増額になる可能性があります。
ただし、通常のリフォームでは建築確認が不要であり、高価な材料の使用や最新設備を導入しても固定資産税は変わりません。
和室を作ると固定資産税が高くなる
和室を作ると固定資産税が高くなる点に注意が必要です。和室は材料費が高いうえに、和室にある家を価値が高いと評価される傾向があります。
実のところ、近年、和室がない家が増えているのも固定資産税の対策のひとつなのです。
なんで和室の無い家が増えてるのかなと思ったら、和室のほうが税金高いのか。
信じられねぇ。
引用:X
リフォームで和室を作るか検討中なら、固定資産税が上がることを覚えておきましょう。
リフォームならリノベーションハイムにご相談ください


リフォームを検討するなら、リノベーションハイムにご相談ください。
リノベーションハイムはセキスイハイムのグループ会社であり、リフォーム実績が50年以上ある会社です。お客様の要望を叶えるプランはもちろん、補助金活用プランや現地調査により適切なプランの提案ができます。
アフターサポートも充実しており、万が一、不具合や問題点が生じても保証範囲内で迅速な対応を行います。リフォームに関して不明点や不安点がある場合には、ご気軽にお問い合わせください。
リノベーションハイムのリフォーム事例
ここでは、リノベーションハイムのリフォーム事例を、2つにまとめて紹介します。
事例①【1,735万円/築16年/東京都】
約15年前に購入した建売をリフォームした事例です。購入当時は気に入っていた家でも長年住み続けると小さな不満が積み重なることから、解消する目的でリフォームを実施しました。
隣地に囲まれている家であるものの、日当たりや風通しは比較的確保できる家です。ただし、1階は電気が必要なほど日の当たる場所が限られていたため、隣接する和室とLDKの空間を一体にしています。
また、家事動線を効率良くするためにL型のコンパクトキッチンを導入し、浴室と脱衣所を2階に移動しました。
事例②【1,774万円/築13年/千葉県】
ホテルのような空間とリモートワークに対応したリフォーム事例です。
和室を無くして大きなLDKを実現しています。もともと和室にあった押入れを洋風に改装し、一部をワークスペースにしました。
扉を閉めるとLDKからは収納に見える仕様です。リモートワーク中は扉を閉めれば仕事の空間にもできます。また、水回りを全て一新し色味をダーク色に統一させたことで、ホテルのような高級感を実現しています。
リフォームの税金にまつわるよくある質問
最後に、リフォームの税金にまつわるよくある質問に、3つお答えします。
リフォームしたら確定申告は必要?
リフォームを実施し所得税の減税措置を受けるには、確定申告が欠かせません。
バリアフリーや省エネなどリフォームを実施後、所得税の減税を利用するには翌年の確定申告の時期に自ら申告する必要があります。必要書類を揃えて管轄の税務署で申告を行いましょう。
リフォームしたら税金は上がる?
リフォームしても税金は上がらないことが多いです。
ただし、増築により床面積や評価額が上がれば、固定資産税の増額は避けられません。活用できる減税制度を利用して、納税額を抑えるのが賢明です。
リフォーム減税の申請方法は?
リフォーム減税の申請方法は、所得税と固定資産税で異なり、次のように行います。
| 税金の種類 | 申請方法 |
|---|---|
| 所得税 | リフォームの翌年に、確定申告を行う |
| 固定資産税 | リフォーム完了後、3ヶ月以内に市区町村役場で申請する |
リフォーム減税では税金の種類により、申請場所が異なる点に注意が必要です。国土交通省の公式サイトより必要な書類などを確認し、スムーズに申告できるように準備しましょう。
まとめ
本記事では、リフォームの実施でかかる可能性のある税金や減税制度を紹介しました。安全で安心な生活をするためにリフォームを行うなら、活用できる減税制度を利用するのが賢明です。
リフォームを行うと、不動産取得税や贈与税などの税金がかかることもあります。そのため、減税制度を利用して可能な限り納税額を抑えましょう。
本記事があなたのお役に立てることを願っております。