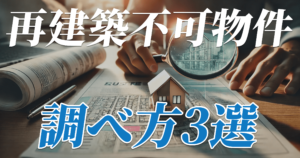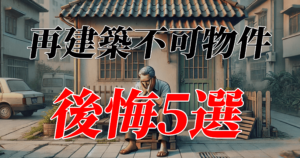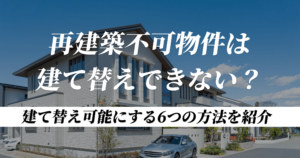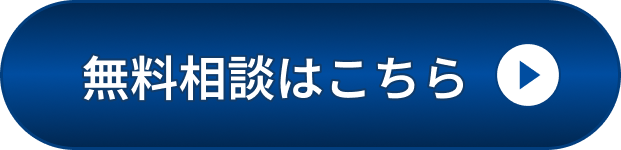「再建築不可物件ってなに?」
「再建築不可物件はどのような活用法があるの?」
再建築不可物件とは、更地にして建て替えができない建物のことを指します。なかには、再建築不可物件を所有しているものの、どう活用すれば良いかわからないという方もいるでしょう。
現状ではリフォームすれば住宅として住める、あるいは賃貸経営をすることが可能です。しかし、2025年4月には建築基準法が改正され、リフォームに関する制限が厳しくなるため慎重に検討する必要があります。
そこで本記事では、建築基準法の改正予定で注意するポイントを交えて、再建築不可物件について解説します。あわせて、リフォームする利点や所有時の注意点を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

リノベーションハイムでは、リフォームの無料相談を受け付けています。
50年以上の歴史と豊富なリフォーム実績からお客様のご要望に応じたリフォームを実現します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
そもそも再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、更地にして建て替えができない建物を指します。1950年以前に建てられた住宅は、建築基準法の条件を満たしていないことが数多くあり、安全性を確保できないため、建て替えができません。
加えて、市街化調整区域(農地や森林といった自然を守るため市街化を抑制する地域)や土砂災害特別警戒区域(土砂災害が発生した際に住民の生命や身体に著しい危害が生じるおそれのある地域)にある住宅は、建築基準法に適合しても建て替えができないことがあります。
市街化調整区域は都市計画法により定められており、市街地の拡大を防ぐ目的で建て替えができません。一方、土砂災害特別警戒区域では住民の安全性を守るために建築確認が必要であり、都道府県の許可が下りなければ建て替えられないのです。
再建築不可物件は築年数の長い建物に加えて、どの地域に建物があるのかといった点が重要になります。
再建築不可物件になる代表的な3つの条件
ここからは、再建築不可物件になる代表的な条件を、3つにまとめて紹介します。
土地が基準法上の道路に接していない(袋地)
建築基準法43条より、土地が基準法上に道路に接していないこと(袋地)は再建築物件になる条件の1つです。袋地とは、道路に全く接していない土地を指します。
袋地は接道義務を満たしていないことから、一度建物が解体された場合、新たに建築する権利がありません。また、火災や地震などの災害で建物が破壊された場合、建て替えが不可能になる恐れがあるため注意が必要です。
土地の接道が2m以上ない(旗竿地)
建築基準法43条より土地の接道が2m以上ないことも、再建築物件になる条件の1つです。
旗竿地とは、道路に接する部分(路地)が細長く、奥まった場所にある土地を指します。旗竿地では避難が必要な際にすばやく逃げられるようにするため、路地の幅が確保できなければ建て替えができません。
旗竿地の場合には自治体により、路地の長さにより路地の幅規定が異なるため注意が必要です。たとえば、東京都の場合は次のような建築安全条例があります。
| 路地の長さ | 路地の幅 |
|---|---|
| 20m以内 | 2m |
| 20m以上 | 3m |
災害時は素早く避難できなければならないため、旗竿地で接道条件を満たさなければ再建築不可物件になるのです。
土地に接する道路の道幅が4m未満
建築基準法43条より、土地に接する道路の道幅が4m未満なことも、再建築物件になる条件の1つです。火災発生時の消火や急病人の搬送が必要な場合に緊急車両の通路が確保できなければ、建て替えはできません。
建築基準法で道路とは、幅4m以上のものを指すと定められています。消防車や救急車などは車体が大きいうえに迅速に現場まで向かうため、スムーズに通行できるよう十分な幅が必要だからです。
素早く消火活動や救命活動ができるように、土地に接する道路の道幅が4m未満であれば再建築不可物件の扱いになります。
自分の家が再建築不可物件か調べる方法
再建築不可物件に該当するかは、次の3つの方法で調べられます。
- 土木事務所もしくは市役所、区役所で調べてもらう
- 自治体のホームページで確認する
- 専門不動産に相談する
再建築不可物件なのかを判断するのは自治体のため、土木事務所もしくは市役所、区役所で調べてもらうことが正確です。ただし、各役所で調べてもらうには4つの必要書類を持参しなければ、判断できないことを念頭におきましょう。
また、自分で自治体のホームページより指定道路図や災害ハザードマップを確認し、再建築不可物件なのか調べることもできます。とはいえ、細かい地図を確認する必要があるため、手間と時間がかかるうえに自己判断でしかありません。
最後に、再建築不可物件を扱う専門不動産に相談できるものの、市役所に比べて確実性は低い側面があります。
なお、再建築不可物件の調べ方に関して詳しく知りたい方は、次の記事も合わせて参考にしてください。
再建築不可物件で後悔した事例
再建築不可物件は、複雑な制限がかかることもあり、後悔する経験をする方も少なくありません。例えば、再建築不可物件を所有して後悔した事例には次のようなものがあります。
- 所有してから再建築不可物件とわかった
- 知識がないまま更地にしたら建て替えができなかった
- 長期間放置してしまった など
知識がないまま再建築不可物件を所有し続けても、固定資産税を支払い続けなくてはなりません。
再建築不可物件は、条件次第では建て替えが可能になることやリフォームができます。後悔しないためにも再建築不可物件の知見を得て、有効活用するのが賢明です。
なお、再建築不可物件でよくある後悔事例をより詳しく知りたい方は次の記事もご覧になってください。
再建築不可物件を有効活用する3つの方法
ここからは、再建築不可物件を有効に活用する方法を、3つにまとめて紹介します。
リフォームする
リフォームすることは、再建築不可物件を有効に活用する方法の1つです。再建築不可物件をリフォームすれば、居住または賃貸経営が可能になります。
ただし、2025年の法改正後は、2階建以下かつ500㎡以下(平屋200㎡以下を除く)の木造建築物のリフォームに対する制限が厳しくなることに注意が必要です。
今まで不要であった建築確認申請が必要となり、大規模修繕・模様替えができなくなります。(鉄骨造やRC造、木造3階建は、現状でも大規模リフォームは不可)
建築基準法の改正前であれば、2階建以下かつ500㎡以下の木造建築物は建築申請不要で大規模リフォームが可能です。そのため、再建築不可物件を所有し、リフォームを検討中の場合は早めに行動しましょう。
なお、再建築不可物件のリフォームに関して、より詳しく知りたい人は次の記事も合わせてご一読ください。
再建築を可能にする
再建築を可能にすることも、再建築不可物件を有効に活用する方法の1つです。再建築が可能になれば、建て替えができるようになります。
そこで、再建築不可の要因を確認し対処可能であれば、実施しましょう。主に、再建築不可になるのは接道義務を果たしていないことが要因であるため、次のような対処ができるか検討します。
- 隣接地を購入する
- 隣接地と土地の等価交換を行う
最終的に再建築が可能かどうかを判断するのは自治体であるため、再建築可能になる条件の相談やアドバイスをもらうことが欠かせません。
更地にする
更地にすることも、再建築不可物件を有効に活用する方法の1つです。建物が倒壊すると近隣住宅に被害を与え迷惑をかけるため、解体して別の用途での利用も検討しましょう。
たとえば、再建築不可物件を更地にして家庭菜園を行うというような活用ができます。また、更地にすることで建物の維持管理費がかからなくなるといったメリットもあります。
前述したとおり、再建築不可物件は更地にすると建て替えができないため、慎重に検討することが不可欠です。かならず、用途を決めてから解体工事を依頼しましょう。
再建築不可物件を所有する際の注意点
ここからは、再建築不可物件を所有する際の注意点を、3つにまとめて紹介します。
建て替えができない
建て替えができないことは、再建築不可物件を所有する際の注意点の1つです。再建築不可物件が倒壊すれば建て替えができないため、住宅を失うことになります。
前述したとおり、再建築不可物件は築年数の長い家がほとんどです。家の老朽化が進み、台風や地震などの自然災害が起きると、倒壊が起きやすく注意しなければなりません。
万が一、自然災害で再建築不可物件が倒壊すれば、大きな問題となります。更地にして土地を所有し続けるか、別の用途で利用するなど住居以外の活用法を検討しなければならないことを念頭におきましょう。
維持費が避けられない
維持費が避けられないことも、再建築不可物件を所有する際の注意点の1つです。不動産を所有すると、かならず固定資産税の納付は欠かせません。
再建築不可物件に住み続けるなら、固定資産税と修繕費程度の維持費で済みます。ただし、再建築不可物件に住まず放置している状態では、固定資産税に加えて近隣住宅に迷惑をかけないように次のような維持費も必要です。
- 庭木の手入れ・雑草の除去費
- 管理費
- 倒壊を避けるための修繕費
再建築不可物件を自分で維持・管理できなければ、管理を近隣住民に依頼するため、管理費が欠かせません。再建築不可物件には居住状況によるものの、維持するのにお金がかかる側面があります。
建物の安全性を確保できない
建物の安全性を確保できないことも、再建築不可物件を所有する際の注意点の1つです。再建築不可物件の建物は旧耐震基準(1950〜1981年)といって震度5までの地震では倒壊しない強度で設計されているものが数多くあります。
ただし、倒壊せずとも建物の破損は避けられない可能性があることを念頭におかなければなりません。加えて、再建築不可物件は接道義務を果たしておらず、工事車両が入れないため修繕工事を行えない場合もあります。
近年、震度5を超える地震は各地で頻繁に起こることもあり、再建築不可物件の安全性確保は困難です。
再建築不可物件のリフォームならリノベーションハイムがおすすめ
再建築不可物件のリフォームなら、リノベーションハイムにおまかせください。リノベーションハイムは、50年以上リフォームを行うセキスイハイムのグループ会社です。
これまでお客様の要望に応じたリフォームを実施した結果、総合満足度85%を得ています。期待以上の空間を実現するためのノウハウや提案力があり、納得感を得るリフォームが可能です。
豊富なリフォーム実績と高いお客様満足度のあるリノベーションハイムでは、資料請求や無料相談を受けつけているため、ぜひリノベーションハイムへ問い合わせください。
まとめ
本記事では、再建築不可物件について詳しく解説しました。再建築不可物件はリフォームをして、活用するのがおすすめです。
ただし、2025年4月に建築基準法の改正が予定されています。これまで無申請で可能であった2階建以下かつ500㎡以下(平屋200㎡以下を除く)の木造建築物でも大規模リフォームの際に建築確認が必要になります。
建築基準法の改正後にリフォームができないとならないためにも、早めに行動するのが賢明です。再建築不可物件のリフォームを行うなら、実績が豊富なリノベーションハイムがおすすめです。お客様満足度が高く、リフォームで要望に応じた空間を実現します。
まずは、リノベーションハイムで資料請求や無料相談をご検討ください。