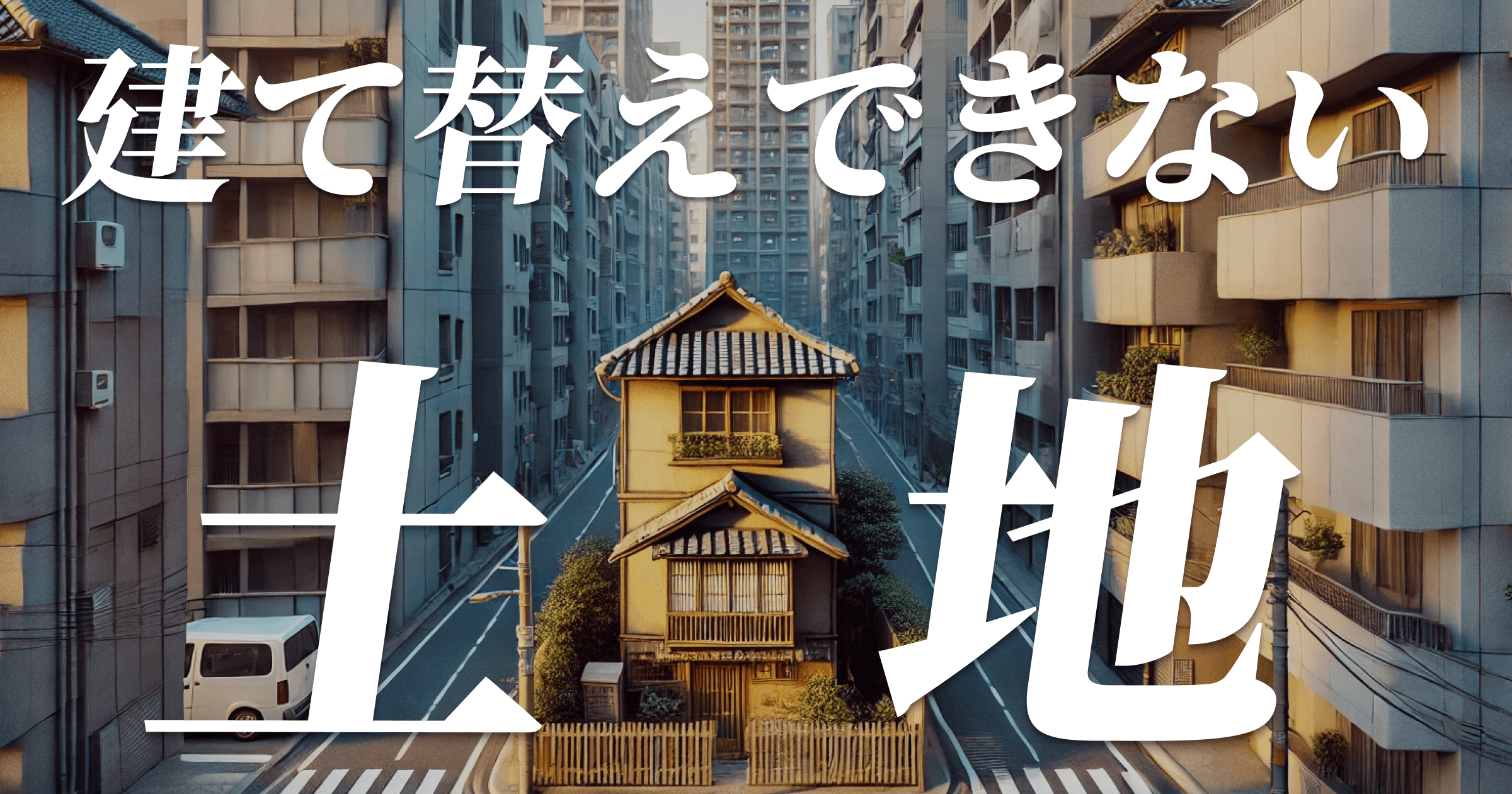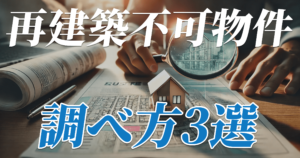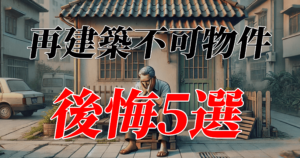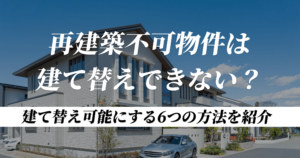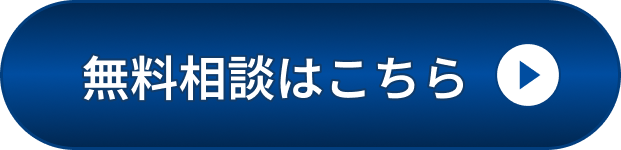「建て替えができない土地を所有するのはリスクが高い?」
「建て替えができない土地はどのような活用法があるの?」
建て替えができない土地を所有しても、デメリットしかないと感じる方は多いかもしれません。実のところ、建て替えができなくてもリフォームは可能です。だからこそ、安価で土地と建物を購入して修繕や修理を行い、居住したり賃貸の経営を行う人もいます。
しかし、建て替えできない土地には注意しなくてはいけないことがあるのも事実です。そのため、事前に必要な知識・情報を入手しておくことが必要です。
そこで本記事では、建て替えできない土地の活用法を3つ紹介します。あわせて、所有で後悔しないためのコツも解説するので、参考にしてください。

リノベーションハイムでは、リフォームの無料相談を受け付けています。
50年以上の歴史と豊富なリフォーム実績からお客様のご要望に応じたリフォームを実現します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
建て替えができない代表的な2つの土地
ここからは、建て替えができない代表的な2つの土地を、2つにまとめて紹介します。
基準法上の道路に土地が2m以上接していない
建築基準法43条より、基準法上の道路に土地が2m以上接していない(接道義務)と、建て替えができません。
具体的には、袋地(他の土地に囲まれ道路と接していない土地)や道路に接しているものの規定の長さ以下の土地が該当します。なかでも特に注意が必要なのが、旗竿地(道路に接する土地が細長く奥まったところにある土地)です。
旗竿地の多くは、規定の長さがある道路に接しています。しかし、接道幅が2mあっても敷地までの細長い土地で2m未満の箇所がある場合は、接道義務を果たしていないとみなされることに注意が必要です。
市街化調整区域に土地があり建築要件に該当しない
都市計画法43条より、市街化調整区域に土地があり開発許可の条件に該当しなければ、建て替えができません。市街化調整区域とは、市街化を抑制するために定められた区域を指す言葉です。
農地や森林を維持するために、市街化調整区域では商業施設や住宅の建設に制限があります。ただし、建て替えの内容次第では自治体の許可が出る可能性もあるため、土木事務所もしくは市役所、区役所で相談するのが賢明です。
建て替えができない土地の3つの活用方法
ここからは、建て替えができない土地の活用方法を、3つにまとめて紹介します。
自宅として住み続ける
自宅として住み続けることは、建て替えができない土地の活用方法の1つです。建て替えができない土地でも修繕やリフォームは可能であり、家を修理しながら住み続けられます。
ただし、2025年4月に建築基準法の改正が予定されているため、リフォームを検討するなら早めが賢明です。
建築基準法が改正されると、2階建以下かつ500㎡以下(平屋200㎡以下を除く)の木造建築物は、屋根や外壁・柱・階段を半分以上変えるといった大規模リフォームができなくなります。(鉄骨造やRC造、木造3階建は、現状でも大規模リフォームは不可)
したがって、大規模リフォームを行うなら建築基準法改定前にしましょう。建て替えができない土地でも修繕とリフォームの内容次第では、自宅として住み続けやすくなります。
太陽光発電設備を設置する
太陽光発電設備を設置することも、建て替えができない土地の活用方法の1つです。
建物の屋根やベランダに太陽光発電設備を設置すれば、電気代を節約できます。もし、発電量が使用量を上回るなら、電力会社へ買取を依頼することも可能です。
ただし、太陽光発電設備を設置して発電ができるのは、日当たりが良い土地に限られます。
近隣に高いマンションなどがあり日当たりが悪ければ、太陽光発電設備を設置しても思うように発電できません。買取どころか節約にもなりづらいことを念頭におきましょう。
リフォームして賃貸経営をする
リフォームして賃貸経営することも、建て替えができない土地の活用方法の1つです。駅近といった通勤・通学に便利で立地が良ければ物件を借りたい人は多いため、家賃で安定した収入を得やすくなります。
賃貸で貸すなら、水回りやキッチンをきれいに掃除して清潔感がある印象を与えましょう。また、ドアや壁などにキズや汚れがあれば、平穏な暮らしができるように交換するのが賢明です。
入居者が気持ちよく住めるようにリフォームを行えば、賃貸で貸しやすい環境を整えられ、家賃収入を得やすくなります。
建て替えができない土地を所有し後悔しないためのコツ
ここからは、建て替えができない土地を所有し後悔しないためのコツを、2つにまとめて紹介します。
再建築可能な状態に変える
再建築可能な状態に変えることは、建て替えができない土地を所有し後悔しないためのコツの1つです。接道義務を果たせば建て替えができる場合には、次のいずれかの条件を満たせると再建築が可能になります。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 隣接地を購入する | 売り出しされており、購入可能な金額である場合 |
| 隣接地と土地の等価交換を行う | 売り出されていないものの、隣接地の所有者との関係性が良好であり、交渉ができる場合 |
隣接地を購入したり、土地の等価交換を行う場合には、接道しなければ意味がないことに注意が必要です。再建築可能な状態に変更できれば、更地にしても建て替えができるため、有効に利用できます。
建物を維持する
建物を維持することも、建て替えができない土地を所有し後悔しないためのコツの1つです。建て替えができない土地を更地にすると、建物を建てられなくなります。
もし、建築年数が長く老朽化が進んでいる場合には、倒壊しないように修繕するなどの対応が必要です。万が一、建物が倒壊すれば土地の用途が住宅でなくなり、住宅用地特例が利用できなくなるため、固定資産税が増額になります。
建て替えできない土地の維持費が高くなることから、建物を維持するのが賢明です。
再建築不可物件は2025年の法改正による影響に注意!
再建築不可物件(2階建以下かつ500㎡以下(平屋200㎡以下を除く)の木造建築物)は、2025年の法改正によって大規模リフォームの着工ができなくなることに注意が必要です。
法改正前は鉄骨造やRC造、木造3階建の再建築不可物件の大規模リフォームは不可でしたが、2階建以下かつ500㎡以下の木造建築物は建築確認が不要であったため、大規模リフォームができました。
しかし、改正後は今まで建築確認申請の必要がなかった、2階建以下かつ500㎡以下(平屋200㎡以下を除く)の木造建築物にも建築確認が必要になります。結果的に2025年の法改正後、再建築不可物件は確認申請に通らなくなり、大規模リフォームができなくなるのです。
リフォームをしようとしても着工ができなくなってしまうため、再建築不可物件(2階建以下かつ500㎡以下(平屋200㎡以下を除く)の木造建築物)をリフォームしたいという方は早めの行動が重要です。
再建築不可物件のリフォームならリノベーションハイムがおすすめ
再建築不可物件のリフォームなら、リノベーションハイムにおまかせください。リノベーションハイムは、セキスイハイムのグループ会社です。50年以上お客様の要望に応じたリフォームを実施した実績があります。
加えて、お客様の総合満足度85%を得ており、リフォームで期待以上の空間を実現するためのノウハウや提案力が強みです。豊富なリフォーム実績と高いお客様満足度のあるリノベーションハイムでは、資料請求や無料相談を受けつけているため、ぜひ問い合わせください。
まとめ
建て替えができない土地を活用するならリフォームを行い、住宅として住み続けるまたは賃貸経営をするのがおすすめです。建て替えができない土地は、地震や台風といった自然災害で倒壊すれば、再建築ができません。
土地の用途が住宅でなくなれば、固定資産税は増額されるうえに、活用法も限られます。リフォームで修繕をしつつ、建物を維持するのが賢明です。
そこで、建て替えができない建物のリフォームを検討するなら、リノベーションハイムにご相談ください。50年以上リフォームを実施してきた経験から、リフォームのノウハウや提案力があります。
まずはお気軽にご相談ください。本記事があなたのお役に立てることを願っております。